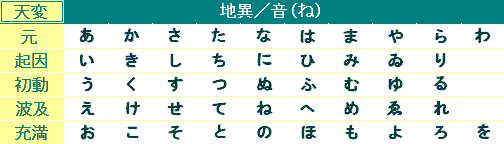|
= ご注意 =
この章は、あくまで個人の妄想的発想・推考であり学術的な根拠はありません。
基本 : 天変地異、総じて「天」の意向を「地」に取り次ぐ役目を致します。
文法 : 同様に上から下に作用する順に連ねて、変化の状態を形容します。
濁音 : その「一音」がもつ作用の最初の段階を示します。
連音 : 相対的反意が両立して「ども」ると「もど」る作用を示す場合があります。
例 はは、ちち、かか、とと、ほほ、みみ、もも、など
*基本的な構成音は、「わ」、「を」、「ん」を除いた二組の相対的な「四十五音」であり
ここでいう「五十音」は二組の「四十五音」が「わ」「を」以って統合されたものとします。
以下、「地」の「ね根」に交差する「天」の
【元】、【起因】、【初動】、【波及】、【充満】
の各五音づつを示します
.
「地の基」
-
あ 「地の基」と「天の元」 相合わさりはじまる作用。
- あ(会、逢、遭、当、充、宛、浴、編、開、明、有、在、或、空、荒、飽、敢、上、挙、揚、吾、彼、和)
あひ(合、相、間)、あふ(仰、扇)ぐ、あは(淡い、併す、哀れ、憐れ)、あらた(改、新)
あらは(露、顕、表す、現れる)、あかし証、あらそ争ふ、あづ預ける、あへ喘ぐ、、、
-
い 「地の基」と「起因」 天元に基づく、従属、従う作用。
- い(生、云、言、行、往、逝、良、好、佳、善、容、入、要、射、活)、いと(厭ふ、愛しい)
いは(曰く、祝ふ)、いき(息、粋)、いや(嫌、厭、癒す)、いくさ(軍、戦)、いさ(勇む、諫める)
いま今、いな否、いか怒る、いそ急ぐ、いきほ勢ひ、いそが忙しい、いとな営む、いまし戒め、、、
-
う 「地の基」へ「初動」 不安定、不確定な作用。
-
う(生、産、浮、受、承、請、売、得、打、討、撃、飢、植、埋、失)、うつ(移、写、映、遷)る
うた(歌、詩、唄)、うば(姥、奪ふ)、うら(裏、浦、恨む)、うれ(憂、愁)ふ、うしな失ふ
うひ初、うへ上、うかが伺ふ、うたが疑ふ、うなが促す、うらな占ひ、うと疎い、うな唸る、、、
-
え 「地の基」へ「波及」 部分、付随に関する作用。
-
え(柄、江、選、得、獲)、えら偉い、えにし縁、えだ枝、こえ肥、、、
-
お 「地の基」へ「充満」 全体、主体に関する作用。(畏怖、尊厳)
-
お(御、起、興、帯、置、生、落、負、追、押)、おも(主、面、思ふ、想ひ、重い)、おぼ(覚え、溺れ)
おく(奥、送る、贈る、遅れ)、おほ(覆ふ、被ふ、大きい)、おそ(恐、怖、畏)れ、おほやけ公
おこな行ふ、おこた怠る、おごそ厳か おどろ驚く、おこ怒る、おど脅す、おび怯え、おや親、、、
.
「地の形成」
-
か 「形成」の「元」 形容に関する作用。(多種多様な形成のはじめ)
-
か(化、変、代、交、貸、仮、借、換、替、勝、狩、刈、苅、飼、枯、涸、欠、駆、書、画、掛、懸、噛、咬)
かた(方、片、形、型、潟、堅、固、硬、難、語る)、かか(掲げる、関はる、抱へる)、かげ(陰、影)
かな(悲し、哀し、叶ふ、適ふ)、から(空、殻、唐、絡む)、かど(角、門)、かんが(考へ、鑑みる)
かくま匿ふ、かたく頑な、かく隠す、かこ囲む、かべ壁、ほか他・・・
-
き 「形成」の「起因」 成育に関する作用。(生命の象徴)
-
き(生、効、利、聞、決、着、木、樹、切、斬、伐、消)、きざ(兆し、刻む)、きず(傷、築く)
きそ競ふ、きは(極、究)める、きずな絆、、、
-
く 「形成」の「初動」 取込に関する作用。
-
く(食、喰、汲、酌、来、暮、悔、組)、くら(倉、蔵、暗い、眩む、比べる)、くだ(管、砕く、下る、降る)
くは(詳しい、加へる)、くず(屑、崩す)、くも(雲、曇る)、くさ(草、腐る、臭い)、くる(狂ふ、苦しい)
くば配る、くすり薬、くはだ企てる、くく括る、くさり鎖、、、
-
け 「形成」の「波及」 変化に関する作用。
-
け(毛、化、蹴、消)、けが汚れ、けず削る、けは険しい、けむり煙、けもの獣、けさ今朝、けふ今日
、、、
-
こ 「形成」の「充満」 要素に関する作用。(成り立ちの素)
-
こ(是、此、子、児、小、粉、込、混、請、乞、媚、来、凝、肥、濃、越、超、焦、漕)、こおり(氷、郡)
こと(言、事、殊、異なる)、こま(駒、困る、細かい)、こは(怖、恐、強)い、こは壊す、ことわり理
こほ凍る、こば拒む、ことわ断る、こぶし拳、こぶ瘤、こな粉、こけ苔、こめ米、こえ肥、こゑ声、、、
.
「地の拠点」
-
さ 「拠点」の「元」 遠隔、先端での作用。
-
さ(去、指、刺、射、差、咲、割、裂、冷、覚、醒、下)、さか(坂、阪、栄え、逆さ、賢し、盛ん)、ささ笹
さが(性、捜す、探す)、さび(寂、淋)しい さそ誘ふ、さば裁く、さむ寒い、さまた妨げ、さむらひ侍
かさ(笠、嵩、重なる)、あさ朝、くさ草、ひさ久、今朝、猛者、さまよふ、、、
-
し 「拠点」の「起因」 堆積、沈殿する作用。(土塊、滴の固まり)
-
し(知、敷、占、強、絞、締、閉、滲、染、浸、沁)、しず(静か、閑か、沈む、鎮まる)、しば(芝、縛る)
しか(然り、叱る)、しげ(重、茂、繁)、しめ(湿る、示す)、しら(報せ、調べ)、しも(下、霜)、しな品
しの(凌ぐ、忍ぶ)、したが(従、随)ふ、しるし(記、印、標、徴)、ぬし主、はしら柱
・ 「し」の作用の最初「じ」、まさしく沈殿(堆積)するその瞬間。 じっとする。
-
す 「拠点」の「初動」 対象が希薄、通過する作用。
-
す(住、棲、巣、洲、据、過、済、捨、透、澄、好、吸、擦)、すす(煤、進む、奨める)、すき隙、すじ筋
すこ少し、すさ荒む、すた廃る、すで既に、す据わる、すわ座る、すな砂、すゑ末、、、
・ 「す」の作用の最初「ず」、まさに対象が希薄で通過する瞬間。 ずれる。
-
せ 「拠点」の「波及」 対象との間隔が縮小した作用。(距離、時間)
-
せ(背、急、競、責、攻)、せき(咳、関、堰)、せま(狭い、迫る)、、、
-
そ 「拠点」の「充満」 対象全体に沿う作用。(実体の側面)
-
そ(沿、添、染、初、反、剃、削、逸)、そな(供、備)へる、そそ注ぐ、そだ育つ、そむ背く、そろ揃ふ
そこ底、そと外、そば側
.
「地の発起」
作用の分岐状態で、相対的な意味を含みます。
-
た 「発起」の「元」 断絶する作用。(相対的に収束)
-
た(発、起、建、立、食、足、貯、溜、断、絶、裁、炊、焚、垂、田、他)、たが(違ふ、互ひ)、ため試す
たず(訪、尋、訊)ね、たび(度、旅)、たける(猛、剛、武)、たうげ峠、たがや耕す、たたか戦ふ、たたず佇む
たも保つ、たね種、たば束、、、
-
ち 「発起」の「起因」 離散する作用。(相対的に凝縮)
-
ち(血、乳、千、散)、ちか(近い、誓ひ)、ちが違ふ、ちぎ契り、ちぢ縮む、ちな因み、ちひ小さい
ちり塵、ちから力、、、
-
つ 「発起」の「初動」 突出する作用。(相対的に継続)
-
つ(津、付、着、就、次、告、接、継、積、詰、突、釣)、つか(束、塚、疲れ、掴む)、つづ(続く、綴る)
つく(造、作、創)る、つつ(筒、包む)、つと(勤、努、勉、務)め、つら(面、辛い、連なる)、つど集ふ
つた伝へる、つつし慎む、つつが恙なく、、、
-
て 「発起」の「波及」 放出する作用。(相対的に抽出)
-
て手、て照る、てる輝、おもて(表、面)、あて宛、かて糧、はて果、はてな?
-
と 「発起」の「充満」 区切る作用。(相対的に次点)
-
と(閉、戸、止、取、捕、獲、採、盗、撮、泊、摂、執、録、飛、跳、問、溶、解、説、研)、とし(年、歳)
ところ(所、処)、ととの(整、調)ふ、となり隣、とびら扉、とりこ虜、とど届く、とき時、、、
.
「地の転成」
-
な 「転成」の「元」 転成の境界に関する作用。(転変の有無)
-
な(名、菜、成、熟、為、亡、無、鳴、泣、啼、哭、投、舐、慣、馴)、なか(中、仲、半)、なが(永、長)い
なほ(直、治)す、なら(習、倣)ふ、なら(並、列)ぶ、なみだ(涙、泪)、なが流す、なげ嘆く、なや悩む
なご和む、なつ懐く、なに何、なぞ謎、なま生、、、、
-
に 「転成」の「起因」 疑似、異種を同様に扱う作用。
-
に(似、煮、逃、荷)、にほ(臭、匂)ひ、にく(肉、憎む)、にが苦い、にぎ握る、にご濁る、にな担ふ
にら睨む、にぎは賑ふ、にせ偽、には庭、にひ新、はにわ埴輪、くに(国、邦)、みにく醜い、なに?
・ 「に」疑似、「し」の最初「じ」まさに滴の固まる(堆積)瞬間。NI-ZI(虹、滲む)。
・ 「お」主体(畏怖、尊厳)、「に」疑似、異種が同様の状態。O-NI(鬼)と申します。
-
ぬ 「転成」の「初動」 付着、絡みあう作用。
-
ぬ(塗、濡、縫、抜、脱)、ぬす盗む、ぬく緩い、ぬぐ拭ふ、ぬめ滑る、ぬる温い、ぬの布、ぬし
-
ね 「転成」の「波及」 密着、へばりつく作用。
-
ね(根、寝、練、音)、ねが願ふ、ねた妬む、ねば粘る、ねぶ舐る、ねむ眠る、ねら狙ふ、ねんご懇ろ
みね(峰、嶺)、つね(常、恒)、うね畝、さね実、たね種、はね羽、ほね骨、くねる、こねる
-
の 「転成」の「充満」 他に転じて延長、拡張する作用。
-
の(乃、野、延、伸、飲、退、乗、載)、のり(規、憲、法、糊)、のぞ(覗く、除く、望む、臨む)、のち後
その(園、苑)、つの角、たの頼む、ほの仄か、ほのほ炎、いのち命、きのふ昨日、海苔、熨斗
.
「地の領域」
-
は 「領域」の「元」 解放に関する作用。(拡散、広がり)
-
は(葉、羽、晴、生、栄、映、這、張、貼、跳、掃、吐、履、剥、馳、腫、果、恥)、はな(話、離、放)す
はか(計、図、測、謀)る、はこ(箱、函、筺、運ぶ)、はば(幅、巾、阻む)、はぐく育む、はず外れ
まは(回、廻、周)り、かは(皮、革、川、河)、こは(怖ひ、壊れる)、さは(沢、澤、触る)、
きは際 には庭 、つはもの兵
-
ひ 「領域」の「起因」 内在に関する作用。(込める)
-
ひ(日、陽、火、弾、曳、引、退)、ひら(平、片、開く、拓く)、ひろ(広、博、寛、洋、拾ふ)、ひかり光
ひそ(密、潜む)、ひらめ閃く、ひび響く、ひな雛、ひき匹、あひ(合、間、相)、こひ恋
-
ふ 「領域」の「初動」 内側に関する作用。
-
ふ(触、拭、葺、吹、噴、降、振、増、殖、踏、伏、臥)、ふた(蓋、双)、ふち(縁、作用)、ふね(舟、船)
ふさ(房、塞ぐ)、ふし節、ふくろ袋、ふところ懐、ふか深い、ふく含む、ふと太る、ふせ防ぐ
-
へ 「領域」の「波及」 周辺に関する作用。
-
へ(重、経、減)、へい(兵、塀)、へだ隔たり、へり縁、へ屁、うへ上、まへ前
-
ほ 「領域」の「充満」 全容に関する作用。(空間)
-
ほ(帆、干、穂、吠、欲、褒、彫、掘)、ほろ(滅、亡)ぶ、ほこ(矛、鉾、誇り)、ほこら祠、ほこり埃
ほら洞、ほり壕、にほ(匂、臭)ふ、とほ(遠い、通る)、しほ(塩、潮、汐)、ほか他、、、
.
「地の合成」
-
ま 「合成」の「元」 混在、混合する作用。(真性、正統、立派)
-
ま(真、間、舞、待、未、曲、巻、増、混、交、蒔、撒、負)、まさ(正、当、勝る)、まつ(祭、祀、奉)る
まと(的、纏め)、まこと(真、誠)、まゐ(参、詣)る、まう設ける、まか任す、まな学ぶ、またた瞬く
まぼろし幻、まぶ眩しい、まく幕、たま(玉、球、霊、珠)、こま(駒、狛)、さま様、つま妻、なま生
* 天と地は元々一つが分離したモノ。よって「混合、混在」を真の正統な在り方としています。
-
み 「合成」の「起因」 結実、具象する作用。(具現の象徴)
-
み(実、身、見、観、看、診、満、充)、みち(道、路、途)、みき幹、みさき岬、みなと港、みなもと源
みにく醜い、みずか自ら、みと認め、みじ惨め、みつ貢ぐ、みが磨く、みな皆、みゆき幸、みさを操
-
む 「合成」の「初動」 結集、集合する作用。
-
む(群、向、剥、蒸)、むこ婿、むし虫、むつ睦、むら村、むろ室、むす結ぶ、むつか難しい、むかし昔
-
め 「合成」の「波及」 結合、合致する作用。(重要、貴重)
-
め(芽、召、女、愛)、めぐ(恵む、巡る)、めく捲る、めひ姪、めし飯、めずら珍しい、めをと夫婦
-
も 「合成」の「充満」 保護、保存する作用。(基盤、土壌)
-
も(持、保、盛、守、喪、漏、燃、萌、面、揉)、もと(基、元、下、本、素、許、求める)、もろ(諸、脆い)
もの(物、者)、もり(森、杜)、もち用ゐる、もど戻す、もぐ潜る、もら貰ふ、もよほ催す、、、
.
「地に停滞」
-
や 「元」の「停滞」 天元に直結する作用。(他に作用がとまる、さえぎる)
-
や(屋、家、谷、矢、止、哉、痩、辞、病、焼、灼、遣)、やす(安、康、靖、休む)、やさ(優、易)しい
やは(軟、柔、和らぐ)、やぶ(藪、破れ、敗れ)、やしな養ふ、やぐら櫓、やつ奴、やど宿、やみ闇
はや(早、速い、囃す)、うやま敬ふ、みやび雅、さや鞘、つや艶、もや靄
-
ゐ 「起因」の「停滞」 固定する作用
-
ゐ(居、井、亥)、ゐなか田舎、くらゐ位
-
ゆ 「初動」の「停滞」 緩和する作用。
-
ゆ(湯、行、往、逝、揺、結、茹)、ゆる(緩、弛)む、ゆが歪む、ゆず譲る、ゆた豊か、ゆだ委ねる
ゆふ夕べ、ゆか床、ゆき雪、ゆめ夢、ゆとり、、、
-
ゑ 「波及」の「停滞」 誘導する作用。
-
ゑ(絵、笑む、酔ふ)、ゑが(画、描)く、ゑさ餌、う(飢、植)ゑる、いしずゑ礎、こゑ声、つゑ杖、
ゆゑ故
-
よ 「充満」の「停滞」 転移、形態を変える作用。
-
よ(夜、代、世、呼、選、因、依、拠、寄、詠、読、良、佳、善、止、避、縒)、よろこ(喜、慶、悦、歓)び
よそお装ふ、よご汚れる、よろ宜しく、よこしま邪、よこ横、よひ宵、よろず万、よはひ齢、よわ弱い
.
「地に定着」
-
ら 「元」の「定着」 接地、安定する作用。
-
らく楽、くら(倉、蔵)、さら(皿、更、新、晒す、曝す)、あらは(顕、表、現)す、はしら柱、あぐら、うら
-
り 「起因」の「定着」 既定、確保する作用。(既存、捕獲)
-
もり(杜、森)、かり狩、つり釣、やり槍、をり檻、きり霧、くもり曇、かかり(係、掛)、へり縁、なり也
-
る 「初動」の「定着」 初期状態に一定する作用。
-
ふる(古、震、奮、揮)、まる(丸、円)、ゆる(許、赦)す、ゆる(緩、弛)む、てる輝
-
れ 「波及」の「定着」 部分を指定する作用。(仮定)
-
おれ俺、かれ彼、たれ誰、われ(吾、我)、きれ布、まれ希、むれ群
-
ろ 「充満」の「定着」 全体を膠着させる作用。(包囲)
-
ころ(頃、転ぶ、殺す)、のろ(鈍、呪)い、おろ愚か、いろ色、しろ城、むろ室、もろ諸、ころも衣
.
「地の構成」
-
わ 「構成」の「元」 構造、組織する作用。
-
わ(吾、我、沸、湧、詫、侘)、わざ(業、技)、わた(綿、腸、渡る、渉る)、わずら(患ふ、煩はす)
わら(笑、嗤)ふ、わず僅か、わめ喚く、わす忘れる、わざは災ひ、わざはひ(厄、禍)、わく枠
わらべ童、わだかま蟠り、、、
-
「WI」構成と起因、?? 「WU」構成と初動、?? 「WE」構成と波及、??
-
* 不明です。
子音となるのはもともとが「九音」であったとします。
二組の組織が存在して、それぞれが各組の「四十五音」を使用していたのではないかという独自の推測からです。
これら二つが統一された結果、「わ」「を」を以って「五十音」とします。
-
を 「構成」の「充満」 伝承、継承する作用。
-
を(男、雄、夫、緒、尾、惜、下、降、小、折)、をさ(長、治、納、修、収)める、をか(岡、丘、陸)
をか(犯、侵、冒)す、をどり踊、をが拝む、をみな女、をし教へ、をろち
-
ん 「・・・」 混沌状態。
-
五十音とは別の概念です。
基本的な子音は九音であり、「わ」、「を」、「ん」は副産物的なものです。
* 「ぬ、の、み、む」等の口語的発音、もしくは転じて使用される場合がほとんどです。
【ぬ、の、み、む、り】等の口語的発音に【ん】がありますが、本意は各【ぬ、の、み、む、り】等です。
例 : 「かみ神-かん」、「かりな仮名-かんな」、「をみな女-をんな」
|