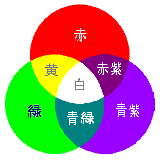
●あお青(青紫)
●みどり緑


「 縄文のひかり」 シンボルマーク |
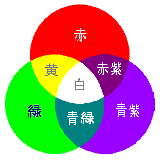 |
光の三原色 | 区分け / 成型 ⇒ | シンボルマーク | |
| ●あか赤 ●あお青(青紫) ●みどり緑 |
 |
 |
|
■ このホームページの 趣旨 ■ - 挨拶にかえて -
【火:カ(クワ)/漢、呉】や、 【日:ジツ/漢、ニチ/呉】は、なぜ、同じ二つの「ひ」と訓読みするのか。また 【赤:セキ/漢、シャク/呉】 【青:セイ/漢、ショウ/呉】 【緑:リョク/漢、ロク/呉】も、なぜ「あか、あお、みどり」と読むのか。
これには「古代のかな」各一音が何を意味していたか?とすべき前提が必要です。 「あをーいろ」# 参照リンク:学研全訳古語辞典
「あを青」には「地」にそう「空」と、同じくそう「海」の色相が重複しており 「あ開」けるともする「ひら開」くでの「ひ」が内在し、 その「ひ」とは 「あか赤」や「あか明」るいに含まれる「か」を繋げて「ひか」り 「そら空」も「うつ空」ろに「うつ映、移」した変化が 「から空」に「あ空」けて「す空」く「あす明日」です。 この「か」とは 「うみ海」或いは雨を含む山河からの水の「み」で 「かみ神」をかくの如く「あが崇」めます。
清音「か」は上下に対し「さか逆」さに「かさ重」なる左右の「さか坂」を 「から空」の「うつ空」ろに「あ空」ける「あ」に「ひ」ともする「か」が 「あか赤」く「あが上」り「あが崇」める「ひ」の対称的な音とすれば
|
|
「み」においては
【見:ケン/漢、ゲン/呉】を「み見」るとするならば 【実:ジツ/漢、ジチ/呉】は、なぜ「み実」なのか。 その実体の 【身:シン/漢、呉】も「み身」だとするならば 【三:サン/漢、呉】が、なぜ「み三」なのか。
「みずか身」らを構成する三音は「み」がはじめなら | ||||||
■ 古語辞典にみる「いろ」の思考例
青の図、即ち是 光の三原色「みへ三重」
平成元年 作図
|
|
■ 古代日本社会の基本構造について
ここで考えられるのは、何らかの理由をもって、三つに区別している民族形体を 男女が一組としてしか対にならない二所帯での、三つ巴の組合せで 各相手方が、重複した光の中心部で潜めている と仮定すると「おもて面、表」に「ひか光」る、三つ巴の色自体が 「天と地と海」各対応する観念を内に合せ持つ、三つの形体が浮かび上がります。 ■ 数学(集合)的「かぞ父」える古代 日本人でありながら「いろは」を知らず「かぞ」えもせず 古来からの成立ちや拠り所たるものに確たる信念や関心すらなく ただ、ここ集合(数学)を把握すれば、上記の疑問は少し解消できるはず です 。 しかしてかたるは 「天と地」を上下の縦軸とし、 「地と海」を左右の横軸とし、同時に 「海と地」上下左右を逆に「海と天」も縦軸とし、 「から空」の「そら空」を「うつ虚」ろに「うつ遷」す 「おもて面、表」に現れない「うら裏、浦」の「う」を取り上げ 「あめ」を含む「みどり」の地からも合流する「み」で「みづ水」とし、 「みづか」らを「みずか」とする貴方自身を「みず」で 「ややこ」しく「あかご」にできたらと思います。 平成十六年三月三日
# 参照リンク「みづ水」/ 学研全訳古語辞典 「みづか自」ら/ 学研全訳古語辞典 「みずか身、親」/ 漢字辞典オンライン ■ 古代数学的史観「 海洋民族幻想 」へどうぞ 一定義で理解できる:海之巻 暗算的に理解すべき:地之巻 古代言語体系の想定:天之巻 管理人:ジヲ門司 |
|
|
|
▲トップ / ホーム |