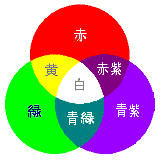


| @/Iroha.nobody.jp/ シンボルマーク |
| 表紙 | 趣旨 | 分析 | 参照 | 読物 |
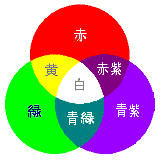
| |
| 区分け 【 光の三原色 】 成型 | |
 |
 |
|
ハジメニコトバアリキ。
天変地異の作用を持つ言葉として検証不可能な古い言語を考察します。 |
|
古代の「いろは」とは何か
・古語辞典によると
「いろは」は実の母に対する総称とされ「かぞ」は同じく父を総称するとあります。この「いろ」二音は、同じ母からという接頭語扱いされています。
・いろ ‥ 同母 |
|
古代の「あを青」とは何か
古語辞典による「あを」本来は、白と黒の間の広い範囲の色とされていますので、白を透明として暗闇との間の変化を示していると捉えてみます。
同母の「いろ」を三音で「いろは」とも二重に示しているならば 「みへ三重」に「み見」る「み三」の実体とする「み実」もなぜ「み身」となるのだろうか。 |
|
「みへ三重」の思考例
「あを青」には「地」にそう「空」と、同じくそう「海」の色相が重複しており、何らかの理由をもって三つに区別している古代日本社会の民族形体を、男女が一組としてしか対にならない二所帯での三つ巴の組合せで、
各相手方が重複した光の中心部で潜む「うら浦、裏」と仮定すると 「おもて表、面」に「ひか光」る、三つ巴の色自体が「空と地と海」各対応する観念を内に合せ持つ、三つの形体が浮かび上がります。 |
空の清き青、見よ。
すなわち是、空の「あ空」けし 「ま間」を照らして「す空」ける かの「はは」日と成り三へに光りて 「▼」表なく「から空」 すなわちこれ「いろ」なり 身の三つに異なる面「●」現す 平成元年 作図
|
|
--- iroha nobody.jp ---
|