ここで展開するのは下記三巻に補足的に「あ充」てた続編になります。
各巻を順に理解したうえで、この外伝も「かなら必」ずお読み下さい。
浦の男性「そ」が海の底から見る空
未明から浦の男性が浜で釣りをしていると、いつの間にか潮が引きはじめ島が見え隠れしだし、潮時ともなると瀬づたいに浜にたたずむ女性が「ひ日」を「あ浴」びていたので、なにげに尋ねてみます。
「今夜中に私は海の底へ戻らなくてはいけません。」と、彼女の答えが不審ながらも一緒に訪ねたら「そこ」は女性だけが住む「みやび」な所でした。ここで見たこともない中間所帯の「うつ」くしい娘に出会い、彼女と幸せに暮らします。
世代は二音「そら」の「つ」
血筋「ひこ」として陸から海へ反転した二世代目の男性となりますが、次世代の息子
「ひひこ」
が誕生する間際に、海の底からは鏡の作用をしない斜めに屈折する「から空」を見上げて溜め息をつくのです。
「愛しの貴方、最近どうかなさいまして?」と、これに答えて
「僕は今こうして海洋に出ているけれど父は山間の出身で、僕に子ができたら羽根を伸ばして、あの空の真下で遊んでやりたいものだ。」
「そ」なら「そと」で「あそ」びましょうかしらと遊び方を説明しだします。
八人の娘が貴方の周りを踊りながら舞いますので、貴方は目を閉じたまま、声がかかるまで決して振り返らず 見てはなりませぬ。
お父様は「かり狩」が生業で、今の貴方は「かり仮」の釣り道具しか無いという事なのね。私の父は「ひた」すの海洋系出身なので、叔父には逆血筋の「たひ」がおります。そこで彼に「み満」ちた道を案内させましょう。
こうして未明すぎ、海洋系「つ」と山間系「か」が「たが互ひ」に入れ替わるのですが、途中、目を閉じている彼には遠くで声が聞こえておりました。
夜明けの晩に「つ」と「か」が入れかわった「うしろの正面だあ・・・」
聞き終わらないうちに彼は思わず目を「あ開」け振り向きました。すると
海から陸に上がるべき「ひひこ曾孫」が、「ひとひ一日」の三世代目で誕生しており、白い髭を生やす姿の「曽祖父」が水面に映し出されたではないか。
驚いて空を見上げると、中間所帯「な」で入れ替わった三世代目では
山間に居たはずの片方の「そ」が「かなた」の空に飛び「さ」るのでした。
「つ」と「か」の「つか」の「ま間」の「まそ」しき ※
鳥居に飛び立つ鳥が居るとするならば、「まさし雅」なりと
無造作に「さかひ境」で「ひ」を振り返り見てはいけません。 |

|
# リンク(参照)
【まそし】/コトバンク 日本国語大辞典 ※
【たひ鯛】/小学館 デジタル大辞泉
【さかひ境】/goo 辞書
|
「長男と次男」及び「末弟と次男」の二組織が複合する新体制としました。
長男の組で海洋と山間のテリトリーが一旦替わり、末弟の組で再度テリトリーを
入れ替えますが、これを完了するには実質上の三世代を要しますので
列島の中間にある
「たが」とは何か
(リンク)も参照して下さい。
海と空では上の「から空」の日を「たた称、賛」えたように、重複する下の
「たが」山間では「そら空」に水を「たた湛」えます。つまり
「かめ瓶」に水を「た溜」める様に「み海」にも水を「み満」たす様に
「そら空」に水を「たた湛」えておかないと「からだ体」へとなるべき
「から空」自体が「そら空」に「うつ移、映」る水面になりません。
また、水からつづく「か」へは
海洋から見る出雲では「みづ水」からを「みづか自」らとし、
出雲から見る山間では「みず水」を下で「みずか身、親」とし、
夫々二世代を以って「からだ身体」を各二対成立させる
独自論とします。
# 参照リンク
「みづ水」/
学研全訳古語辞典
「みづか自」ら/
学研全訳古語辞典
「みずか身、親」/
漢字辞典オンライン
「たた湛」える/小学館 デジタル大辞泉
二組の四十五音による「か」
重複融合する「たが」
により、互いひに「たが違」ふ
浦として、山間の末弟が海洋の長兄と対峙することになり
海「あいうえお」
の縦を「さかさ」に構成する「四十五音」とします。
浦の「そ」では海洋と「そ」つくりに作る語り口になり
中間「う」でも山間に「うつ」るように「うり」ふたつを認識します。
空も「うつ空」ろに作用するのですが
上の「から空」を映した「そら空」で、ふたつの「か」が虚ろに揺れ動き
両者「からか」ふ「か」の争うが如く、潮の満ち引きによって島が
陸に「うか浮」び上がり、世代ごとにたがへて上下の「か」が反転します。
「ひ日」が「ひた浸」ると同時に
「か日」も「かく隠」れ「つつ」、つづく
「あす」の「か」では「ちが交」ひて「ま交」じり「あ遭」はせぬよう
「ととり飛鳥」が下の「そら空」と「から空」に飛び「か交」ふのです。
我々が見ている空は元来ここで言う「から」なのですが
後に天孫降臨という逆転劇で反転し「そら空」で定着します。
# 参照リンク
【からかふ】/小学館 Domani
【飛び交ふ】/小学館 デジタル大辞泉
【ちが交】ふ/学研全訳古語辞典
「さき先、前」の「さ」と、前後に表裏一体の「つ」と「か」
そもそも、単一融合の時点で先に縄文系血筋で誕生したのは末弟でした。
複合融合の純粋な縄文血筋が途絶える「まぎは間際」でも末弟からです。
さらに重複融合でさえ「さき前、先」に成立させるのも末弟とします。
五十音順では「あ」のあとに「さ」がきますが、末弟の「さ」行を以って
ここでは「さき先」とし、「あ」は「あと後」回しにします。
これらは「さき前」でもある前後が「まへ前」と「うしろ後」でもあり
純粋な縄文男性「うら裏」が先に「まへ前」二音で立ち
同山間の縄文女性「おもて表」は「うしろ後」三音で立ちます。
「うら裏」である山間代表を「まへ前」の「た」とし、
本来の表である海洋代表を「うしろ後」の「た」で貼ると「たた」。
平面的「せなか」と同「おなか」が向かひ合ひ、単なる人が
前後に「かた方」面ごとの二人で互ひに膨らみをもつ人間になります。
海洋「つ」と山間「か」には、夫々の「四十五音」に「た」があり
末弟から組織する「たた」は同じ音でも、長兄から言う「たた」とは
異なる所帯、或ひは作用だと判断しないといけません。
二組の四十五音で「なぞ」ると、その前後が「なぞ謎」の作用になるので
彼らは「そら空」で「した」ように「海と山」に関わる「つ」と「か」を
貴方も「そら諳」むじていただくと「さち幸」の
「さ」でございます。
「かく斯」して海洋系の「か」から転ずる「こ子」は「ひそか間」に
「かく隠」された様に「つな綱」で「な」を区切り、「つな繋」ぐ様に
一組は水に「つ浸」かると二組目は「か」から斜めに「た」へ伝へます。
「かう斯」して言語は「つ」と「か」の二組で「つか使」ひます。
兄の海洋系「つ」と、重複融合による次男の中間で「ま曲」がる「か」を
弟での山間「か」とすべく新規の組織体系、即ち言語とします。
「こう斯」して海洋系「ひこ孫」の代表血筋の流れは、中間所帯で
斜めに「ま曲」がり「まご孫」となる山間における純粋な縄文を継ぐ
濁音の「が」所帯を「ご」へ「さかさ」にした末弟で定着します。
重複融合で一組目の「ま間」を「
ひそか間
」とする間は
「ひこ」を隔世代で一代とするには「まだ」の世代間であり、中間の
「あひだ間」は、白の見えない状態の並びで「まだら斑」とします。
二兄弟が「まだら斑」に集団生活をする「むらむら村々」を
山間における「海洋と山間」が対峙する「むらむら斑斑」とも致します。
「かう斯」して海洋と山間では、夫々が「まだら斑」の状態で区別し、
「まく幕」を「しま島、縞」模様とする「しろぎぬ縞」とも申します。
# 参照リンク
「かう斯」して/コトバンク 日本国語大辞典
「むらむら斑斑」/学研全訳古語辞典
「しろぎぬ縞」/漢字辞典オンライン
斜めに組む四十五音の「なぞ」
「長男と次男」及び「末弟と次男」の二組織が複合する新体制としましたので
長男の組で「海洋と山間」のテリトリーが一旦替わり
末弟の組で、再度、テリトリーを入れ替えるためには
次男の中間所帯を介在し、三つ巴となるべき三つ目の「四十五音」が必要です。
単一融合の中間「か」と複合融合の中間「な」
単一融合では海洋系の中間「か」が抜け出し、この「か」とで
山間組織が二世代一組で縄文血筋を継承する体制としました。つまり
海洋組織は単一融合「か」が移動して中間所帯がありません。
その後「海洋と山間」の世代がずれた代表男性である二兄弟が
立て続けに次男の中間所帯で各横並びに複合融合します。しかし
中間所帯同士の「かが」は直接的に重複する所帯なので、この時点で
複合融合の中間「な」は「あな穴」の「あ空」いたように
あたかも中間の「か」と同様「な」が「な無」いのです。
単一融合「あ・か・さ」
複合融合「た・な・は」
重複融合「ま・や・ら」
つづく夫々の次世代で各次男が誕生し、中間の「な」へ移動しますので
男女の縦横を逆に組む、中間所帯に「四十五音」を斜めに構成します。
夫々が二世代目で血筋を継承すべく、夫々の「あな穴」を通じて
各相手方となる山間組織で二組の「な亡、無、成、名」が生じます。
= 留意事項 =
二組に同じ「な名」が成立し、異なる所帯、作用を示すだけではなく
三段融合「あたま」音を下段に位置するように右の「さ」を左に回し、
さらに一回転しながら各「あたま」を「な」の回りに八つ認識させます。
全所帯からも、各三血筋ごとに移動することを前提に
末弟所帯「は」行の「ひ日」も中間所帯の長男にあたり
これに連れ、同様の「か日」も刻々と「な」を中心に上下一周します。
斜めに組むと「かど角」になる四つと
上下と左右の「すみ角」に四つの計八つの「あたま」で
中間「な」の回りに8つの「四十五音」を丸く構成させます。
本流からすれば残り7つの「四十五音」を同時に聞き分けますので
例として中間所帯の「か」からでは「かしら頭」ともします。
「あたま頭」と「かしら頭」では同一人物を示す場合と
「あたま頭」と「あたま頭」は異なる人物を示すという
{からだ体」が一つでも頭が八つある仕組みの「なぞ」です。
はたして中間的血筋の形態で生まれてきた「次男の宿命」なのか
縄文言語はもとより、大陸言語、上記八つの「四十五音」を含め
出雲から列島に「ち散」らばる所帯で使用する複数の訓読みを
相対的な逆血筋の「みみ」でまとめられる次男の人物像は
「とを十」の言語で使いこなす超人的想定となります。
# リンク(参照)
【とを十】/コトバンク
|
異なる三血筋を帯びてくる各所帯
左図「たすき」を単に背中で回すだけでは、両肩に見える二面は同じです。
帯状の「おもて」を、中間で左右に認識している兄弟姉妹の各所帯に見立てて
両組織の三血筋の流れを下記に説明します。
左右の二兄弟が、夫々の重複融合で各「なな斜」めに中間所帯と交わり
男女の各代表では同世代となる左右の両所帯を「おもて面、表」とします。
しかし、前項までの説明では右方の
弟所帯だけ血筋を逆に反転
したので
代表男性の海洋「はし端」に「おは」す代表二兄弟の各「はば」を
山間代表男性の「はじ端」に「おば帯」し、新規に接点と「す為」べく
逆血筋の弟が背中を向け、右方の組だけ「しりへ」手に裏表を張り合わせます。
すると「たすき」の面が表裏の区別ができない状態の
【メビウスの帯】が出来上がります。
# 参照リンク
【メビウスの帯】/小学館 デジタル大辞泉
【おば帯】す/コトバンク
【しりへ後方】で/
goo 辞書
右の図では、正規の海洋代表と山間「うら浦」の男性同士が左右に対峙され
山間「おもて表、面」が海洋へ変わる「つら面」の二音で「うら裏」とします。
上下と左右へ各斜めに血筋が流動する
兄の「た」血筋を表からたどると、弟「た」へ裏で繋がり「そ」の「あと後」で
表は「うしろ後」にひねられ最初の兄「た」へ「はじめ元」の血筋が戻ります。
兄が下に「た」をつくれば、弟は上に「た」をつくり
兄が上に「た」をつくれば、弟は下に「た」をつくり、「かなら必」ず
「つね」の「ね音」も「もと許」の中間「か」へ「かた語」りつなぎます。
「長男と次男」と「末弟と次男」とを左右に見立て、次男所帯の
中間でねじれる「たすき」の帯を間で「さ裂」いていくと
4つにねじれる、さらに大きな一つの「わ輪」が
「メビウスの輪」
として出来上がります。
言語編「わ」と「を」を用いた「五十音」
「たすき」を「さ裂」いたことにより「みづ」からの山間の「そ」血筋で
列島全体を「ほそ細」長い「ほ穂」の「みづほ」とします。
海洋系では「みず水」と「ひ火」の関係「ほ火」とします。
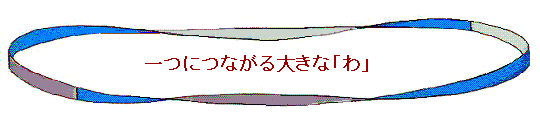
縄文晩期にかけ西日本では人口が壊滅状態となり、同じ環境に近いであろう大陸部でも何千年もの間、人が住まない地域も存在していたかと思われます。
この大陸部の「へり縁」に、我が縄文「海洋民族」が別組織で「くに州」を構え、三つの異なる形態で兄弟姉妹が誕生していたとします。展開してきた複合融合の同時期では、大陸部周辺でも同様の縄文遺跡が出土してくる事になります。
列島から西に沈みゆく「ひ日」として、大陸に誕生する縄文系血筋の男女が
逆に、海からわたり「く来」るとします。列島の地で組織した「わ和」と
下からも「す州」を「くく括」る大陸組織からの「くに州」も「わ倭」とします。
二つの「す州」を一つに「な為、成」す事で、中間「な」へ移動し合う
「さ」行の末弟所帯でも「すす為為」としつつ、名へ「そ染」まり
末弟との構成で、これに「そな備、具、供」えます。
各血筋を示す基本の音は、異なる三所帯から誕生する三血筋での9音であり
「わ」は血筋そのものでもなく、両組織を「くく括」り付ける意味合いとして
「を」も考案します。この音も血筋を示すものではなく、これらを
相手方と構成するための便宜上「わ」と「を」とします。
組み合う相手は相互の
継承伝承する作用「を」を冠して
海洋では「を-のこ」あるいは「をとこ」
山間では「を-みな」あるいは「をとめ」
これら男女が、以下の融合体系として結びます。
最初の単一融合から、次男との複合融合へと各血筋も「うす」れてしまい
「わ」を組織に構成することにより、海を隔てた「融合の縄文人」との
「わ」の組み合わせによる「縄文人同士の融合体系」へと大成します。
「を」を組織化した事で旧融合制度の役目も「を終」ふとします。
# リンク(参照)
【すす為為】/小学館 デジタル大辞泉
【くは加】ふ/学研全訳古語辞典
【を終】ふ/学研全訳古語辞典
【そ十】/コトバンク ※
一組織の区切りを「とを十」として数に「くは加」へ
上記二つの組織は「とを」を「とをを」に「くく括」りで統一します。
この「わ」の作用では二つの「くに州」を「わ割」ることが可能で
ここのつを数えている古代
の数学的史観では割り算といたします。
新規「わを」もちひて「た」ふとしとなす事で
二組織の代表血筋「たた」も「ふと太」く作用し、単なる人ではなく
間を介する状態を人間とする「ふく膨」らみをもつ社会が構成されます。
わたくしたちは
「わた」を海原として「そ十」れにつれ ※
「そら空」の山間代表「そ」も概念を「ふく膨」らませ、壮大な
意味合いも含め全部「そら宇、宇宙」に込めていきます。
 。
「わを」を加えた事で「天地開闢」とする
海洋の縄文血筋を山間の中間「かが」やく「ひかり」の中に閉じ込めて
縄文言語も無くす意味合いと同時に、宇宙を「な名」付ける事により
自然及び全容の各作用も、新生に「な生、成、慣、馴」らしめます。
単一融合「さ」行の末弟所帯を反転する「そ」が最初の代表男性ならば
複合融合「は」行の末弟所帯で認識する「ほ」も上記の血筋が「つ継」がれます。
# 参照リンク
「み実」のならない「はな」/
漢字辞典オンライン
【は帯】く/学研全訳古語辞典
【ひ秀】づ/goo 辞書
【ほ秀】/goo 辞書
【ほ火】/goo 辞書
|
・兄の、左端の長男は「天変」の元で「は」 |
・間の、左縁の長男は「天変」に起因「ひ」
・間の、中間の次男は「天変」の初動「ふ」…
「ふく含」む「ふく膨」らむ
・間の、右縁の末弟は「天変」が波及「へ」
「ふ増」やす「ふと太」い等
|
|
・弟の、右端の末弟は「天変」が充満「ほ」 |
兄と次男では「は」と「へ」で組み、二組で組織化する
次男と弟では「ひ」と「ほ」で組むのが、新規融合のまとめ
でした。
「ほ火、秀、穂」の「ひ秀」づる音変化では
「ひ火」も「ほ火」へ複合で「つ付、突」きかへ、重複融合では
「ほ火」が「ほ火」と重なる「ほのほ炎」となり
「わ」では「ほほ」と二組の血筋が直接つながり
「ほほ」から全血筋の流れが八所帯で「めぐ回」り「な凪、和」ぐと
「か交」や「ま交」も「あ和」へて、最初の「あ」に戻り
「な名」が「な生」り「な成」りて、上下に「な和」り「あが和」り
「あま」と「あめ」で
天地開闢 の
五十音分析
といたします。
# リンク(参照)
【火火出見尊】/コトバンク
【穂穂手見命】/コトバンク
「ほ火、穂」の血筋を帯びる
最初の山間代表「かそ父」に戻る
|
 。
。